 その他
その他 色彩
 その他
その他
私たちが普段何気なく目にしている「色」。実は、この色は、光と物体と私たちの目の複雑な連携プレーによって生まれているのです。
太陽や電灯などから発せられた光は、あらゆる方向に進みます。そして、その光の一部が物体にぶつかると、一部の光は吸収され、一部の光は反射されます。この時、物質の種類によって、どの波長の光を多く反射し、どの波長の光を多く吸収するかが異なります。例えば、赤いリンゴの場合、赤い光の波長を強く反射する性質を持っています。反対に、他の色の光、例えば青い光や緑の光などは吸収してしまいます。
私たちの目は、この反射された光を捉えます。リンゴから反射された光は、主に赤い光なので、私たちの目は「赤い」という情報を受け取り、脳に伝達します。そして、脳はそれを「赤いリンゴ」だと認識するのです。
このように、色とは、光が物体によって反射され、その反射した光を私たちの目が捉え、脳が解釈することで初めて認識されるものなのです。一見単純な「色」の仕組みですが、そこには光と物体と人間の感覚の不思議な連携が隠されていると言えるでしょう。
Read More
 その他
その他 色の恒常性:肌の色の見え方の秘密
- 色の恒常性とは?私たち人間は、太陽の光を浴びて輝くりんごを見て「赤い」と感じ、曇り空の下で見ても、同じように「赤い」と感じます。また、夜、部屋の電気の下で見ても、やはり「赤い」と感じます。これは当たり前のことのように思えますが、実は驚くべき能力によるものなのです。私たちの目は、光を信号として脳に送ることで、色を認識しています。太陽の光、曇り空の光、電球の光は、それぞれ微妙に色が違います。そのため、私たちの目に届く光の波長は、照明によって変化します。もし、私たちの目が、目に届いた光の波長をそのまま脳に伝えていたら、同じりんごを見ても、照明によって違う色に見えてしまうはずです。しかし、実際にはそのようなことはありません。これは、私たちの脳が、照明による光の変化を考慮して、物の色を補正しているからです。これを「色の恒常性」といいます。色の恒常性のおかげで、私たちは、周囲の照明条件に左右されることなく、物の色を本来の色として認識することができるのです。色の恒常性は、私たちが日常生活を送る上で、非常に重要な役割を果たしています。もし、色の恒常性がなかったら、私たちは、常に変化する光の条件の中で、物の色を正しく認識することができず、混乱してしまうでしょう。例えば、料理の色を正しく認識できずに、料理が焦げてしまったり、生焼けのまま食べてしまったりするかもしれません。また、信号の色を正しく認識できずに、事故に遭ってしまうかもしれません。
Read More
 その他
その他 メタメリズム:光のマジックを楽しむ
私たちは普段、何気なく物の色を見ていますが、同じ物を見ても、見る場所や時間帯によって色が違って見えることがありますよね。例えば、洋服店で気に入って買った服の色が、家の照明の下では違って見える、なんて経験はありませんか?
これは「メタメリズム」という現象が関係しています。メタメリズムとは、同じ色として認識していても、光の当たり方によって色が違って見える現象のことです。
私たちの目に色として認識されるのは、物体が光を反射して目に届くからです。しかし、光には様々な種類があり、太陽光、蛍光灯、白熱灯など、光源によってその成分は異なります。
そのため、同じ物体であっても、光源が変わると反射する光の波長も変化し、色の見え方が変わってしまいます。これがメタメリズムの正体です。
メタメリズムは、洋服の色選びだけでなく、絵画の鑑賞や印刷など、様々な場面で見られます。特に、色を扱う仕事をしている人にとっては、メタメリズムを理解しておくことが重要です。
Read More
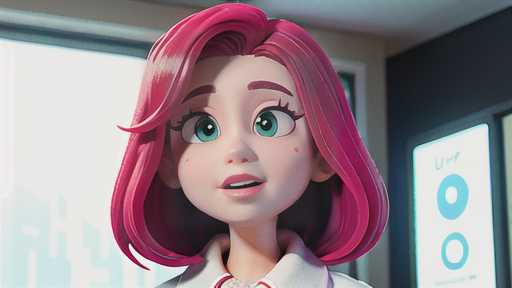 その他
その他 色の明るさのひみつ:明度ってなに?
私たちは普段、何気なく色を識覚し、その情報を生活に役立てています。例えば、白い服を着ると明るい印象に、黒い服を着ると落ち着いた印象になることを経験的に知っています。これは、色が持つ「明度」の違いによるものです。
明度とは、色の明るさの度合いを表す概念であり、白から黒までの間の明るさを示します。色の三属性である色相、彩度、明度のうちの一つであり、明度は色の明るさの度合い、彩度は色の鮮やかさの度合い、色相は赤や青といった色の種類を表します。これらの三つの要素が組み合わさることで、私たちは多様な色を認識することができます。
明度は、私たちの視覚に直接訴えかける要素であるため、デザインやファッションなど、様々な分野で重要な役割を担っています。例えば、明るい色は軽快さや爽やかさを、暗い色は重厚感や高級感を演出する効果があります。また、明度のコントラストを効果的に利用することで、デザインにメリハリをつけたり、情報の重要度を視覚的に表現したりすることも可能です。
日常生活においても、色の明るさを意識することで、周囲に与える印象をコントロールしたり、より快適な空間を作ったりすることができます。例えば、寝室には落ち着いた雰囲気の暗い色を、リビングには明るく開放的な雰囲気の明るい色を選ぶと良いでしょう。
Read More
 その他
その他 色の不思議:アイソメリズムとメタメリズム
私たちは日常生活で、何気なく色を見ています。信号の色や洋服の色、食べ物の色など、色を認識することで私たちは多くの情報を得ています。しかし、私たちが「同じ色」だと認識している色は、本当にすべて同じ色なのでしょうか?
実は、「色が同じように見える」ということには、いくつかのパターンが存在します。
まず、実際に物理的に同じ色の場合です。これは、光を反射する物体の性質が全く同じで、私たちの目に届く光の波長が全く同じである場合です。例えば、工場で大量生産された同じ製品の色は、このパターンに当てはまります。
次に、異なる色なのに、人間の目が同じ色だと認識する場合です。私たちの目は、周囲の環境や光の当たり方によって、色の見え方が変化することがあります。例えば、明るい場所では白っぽく、暗い場所では黒っぽく見えることがあります。また、周囲の色との関係によって、同じ色が違って見えることもあります。これを「色の対比」と呼びます。
さらに、色の見え方には個人差があるということも忘れてはなりません。同じものを見ても、人によって色の感じ方は微妙に異なります。これは、年齢や性別、目の状態、さらには育ってきた環境などが影響していると考えられています。
このように、「色が同じように見える」ということの裏には、様々な要因が複雑に関係しているのです。普段何気なく見ている色も、少し視点を変えて見てみると、新しい発見があるかもしれません。
Read More
 その他
その他 化粧品の色味を数値で読み解く:三刺激値
私たちは日々、空の青、花々の鮮やかさ、夕焼けの温かさなど、色とりどりの世界に囲まれて暮らしています。しかし、私たちが「赤い」と感じる色も、「青い」と感じる色も、人によってその感じ方には微妙な違いがあります。色の感じ方は主観的なものであり、客観的に伝えるのが難しいものです。
そこで、色の見え方を共通の基準で理解し、正確に伝えるために、色を数値で表す方法が開発されました。この方法を用いることで、色の微妙な違いを数値で明確に表現することができます。
色の数値化の方法の一つに、「三刺激値」と呼ばれるものがあります。これは、人間が色を認識する仕組みを利用したもので、赤、緑、青の光の三原色の組み合わせで、すべての色を表現することができます。それぞれの色の光の強さを数値で表すことで、その色がどのような色合いなのかを客観的に示すことができるのです。
Read More
 その他
その他 色の明るさのひみつ?!~明度ってなに?~
私たちは普段何気なく色を見ていますが、ひとつの色を認識する際には「色み」「明るさ」「鮮やかさ」という三つの要素を無意識に感じ取っています。この三つの要素は色の三属性と呼ばれ、色を表現する上で欠かせないものです。
今回のテーマである「明るさ」は、光の色をどれくらい感じるかを表す尺度で、明度と呼ばれることもあります。明度は白と黒を基準に段階的に表され、白に近づくほど高く、黒に近づくほど低くなります。例えば、明るい黄色と薄い黄色は同じ黄色でも明るさが異なります。明るい黄色は明度が高く、薄い黄色は明度が低い黄色と表現できます。
明度は色の見え方に大きく影響を与えます。同じ色でも、明度が高いほど明るく鮮やかに見え、逆に明度が低いほど暗く沈んで見えます。そのため、デザインやファッションなど、色の組み合わせを考える際には明度を意識することが非常に重要になります。例えば、明るい色と暗い色を組み合わせることで、メリハリのある印象的な配色を作ることができます。
Read More
 その他
その他 色の三属性で理解する、化粧品の選び方
私たちは日常生活の中で、空の青、草木の緑、夕焼けの赤など、実に様々な色を目にします。そして、同じものでも、朝と夕方では色の見え方が変わって見えることがありますよね。これは、光の当たり方や周りの環境によって、色の見え方が変化するためです。
しかし、どんな色でも、「色相」「明度」「彩度」という三つの要素で表現することができます。これを色の三属性といいます。
「色相」とは、赤、青、緑など、色の種類を表す要素です。虹を思い浮かべてみてください。虹には赤、橙、黄、緑、青、藍、紫といった色が並んでいますが、これが色相の違いです。
「明度」は、色の明るさを表す要素です。例えば、同じ赤でも、明るい赤と暗い赤がありますよね。これは明度が異なるために起こる違いです。明るい色は白に近く、暗い色は黒に近くなります。
「彩度」は、色の鮮やかさを表す要素です。彩度が高い色は、くすんでおらず、鮮やかに見えます。反対に、彩度が低い色は、灰色がかってくすんで見えます。
この色の三属性を理解すると、色の見え方の仕組みや、色の組み合わせ方をより深く理解することができます。例えば、色相が近い色を組み合わせると、調和のとれた落ち着いた印象になりますし、反対に色相が大きく異なる色を組み合わせると、互いの色を引き立て合い、鮮やかで活動的な印象になります。また、明度や彩度を調整することで、色の印象を大きく変えることも可能です。
Read More
 その他
その他 化粧品の色彩設計における三刺激値の役割
- 色の数値化
私たちは普段、空の青、夕焼けの赤、草木の緑など、様々な色を目にして生活しています。
しかし、これらの色を客観的に表現する方法は、感覚ではなく数値で表す必要があるため、容易ではありません。そこで用いられるのが「三刺激値」という考え方です。
人間の目は、光の三原色である赤、緑、青を感じ取ることで、色を認識しています。この光の三原色の組み合わせを数値化したものが「RGB表色系」ですが、人間の目の特性上、色の見え方には個人差が生じてしまうという問題がありました。
そこで開発されたのが「XYZ表色系」です。
XYZ表色系では、RGB表色系をベースに、人間の視覚特性を考慮した上で、色をX、Y、Zの三つの数値で表現します。
このXYZ表色系におけるX、Y、Zの値こそが「三刺激値」と呼ばれるものです。
三刺激値を用いることで、私たちが目で見て感じる色の情報を、数値という客観的な指標で表現し、他者と共有することが可能になります。
例えば、化粧品の開発現場では、微妙な色合いを正確に再現するために、この三刺激値が活用されています。
Read More
 その他
その他 夜空の魔法?プルキンエシフトで変わる色の見え方
夕暮れ時、空を茜色に染めながら太陽がゆっくりと地平線に沈んでいく時、世界は昼間とは違う顔を見せ始めます。あたりが薄暗くなっていくにつれて、私たちの目に見える色の見え方も少しずつ変化していくのを感じたことはありませんか?
例えば、昼間は太陽の光を浴びて鮮やかな赤色に見えていた花が、夕暮れ時になると、周りの風景に溶け込むように暗くくすんで見えることがあります。 反対に、昼間はそれほど目立たなかった緑色の葉っぱが、夕暮れ時になると、まるで内側から光を放つように、明るく鮮やかに浮かび上がって見えることもあります。
このような、夕暮れ時に起こる色の見え方の変化は、「プルキンエシフト」と呼ばれる現象によるものです。人間の目は、明るい昼間は主に赤色の光に敏感に反応し、暗い環境では青色の光に敏感に反応するようにできています。そのため、夕暮れ時になり周囲が暗くなってくると、私たちの目は、赤色の光よりも青色の光をより強く感じるようになり、その結果、色の見え方が変化するのです。
Read More
 その他
その他 照明マジック!プルキンエ現象でメイクアップ
- プルキンエ現象とは?人間の目は、周囲の明るさに応じて、色の見え方が変化します。明るい場所では、太陽の光を浴びて、色とりどりの世界が広がっていますが、夜や薄暗い場所では、景色全体が青みがかって見える経験をしたことはありませんか? このように、周囲の明るさによって色の見え方が変わる現象をプルキンエ現象と呼びます。この現象は、19世紀のチェコの生理学者であるヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニェによって発見されました。彼は、夕暮れ時に赤い花と青い花を観察したところ、明るい時間帯には赤色が鮮やかに見える花が、暗くなると青色の花よりも早く色を失い、逆に青色の花は暗闇の中で白っぽく輝いて見えたことから、この現象に気づいたと言われています。プルキンエ現象が起こる理由は、私たちの目の網膜にある視細胞の働きが関係しています。網膜には、色を識別する錐体細胞と、明暗を識別する桿体細胞の2種類が存在します。 錐体細胞は明るい場所で活発に働き、赤や緑、青の光にそれぞれ反応することで、私たちに色の違いを認識させてくれます。 一方、桿体細胞は暗い場所でよく機能し、特に青色の光に敏感に反応します。明るい場所では錐体細胞が優位に働くため、私たちは様々な色を鮮やかに感じ取ることができます。しかし、周囲が暗くなると、錐体細胞の働きが弱まり、代わりに桿体細胞が優位になります。 桿体細胞は青色の光に特に敏感であるため、暗い場所では相対的に青色が強調されて見えるようになり、これがプルキンエ現象の正体なのです。
Read More
 その他
その他 色のマジック:減法混色の世界
- 色の三原色
絵の具や印刷など、光を反射して色を表現する際には、色の三原色と呼ばれるものが存在します。色の三原色とは、シアン、マゼンタ、イエローの三色です。これらの色は、他の色を混ぜても作り出すことができない特別な色であり、あらゆる色を作り出すための基礎となります。
色の三原色は、光を吸収する性質によって色を見せる減法混色という仕組みを用いています。それぞれの色の関係を見ていきましょう。
* -シアン-は、光の三原色のうち赤い光を吸収し、青い光と緑色の光を反射します。そのため、私達の目には青緑色に見えるのです。
* -マゼンタ-は、緑色の光を吸収し、赤い光と青い光を反射するため、赤紫色に見えます。
* -イエロー-は、青い光を吸収し、赤い光と緑色の光を反射するため、黄色に見えます。
これらの三原色は、混ぜ合わせることでさらに多くの色を作り出すことができます。例えば、シアンとマゼンタを混ぜると、両方の色が吸収する光が増え、最終的に青い光のみが反射されるため、青色になります。
このように、色の三原色は、光と色の関係を理解する上で重要な要素です。身の回りの印刷物や絵画など、様々な場面で応用されている色の三原色の仕組みを、これを機に意識してみてはいかがでしょうか。
Read More










