
コスメを知りたい
先生、『SD法』って、化粧品の使い心地を調べる方法としてよく聞くんですけど、どんな方法なんですか?

コスメ研究家
良い質問だね!『SD法』は、簡単に言うと、反対の意味を持つ言葉を使って、化粧品を使った時の印象を測る方法なんだ。例えば、『さっぱりしている』⇔『しっとりしている』のようにね。

コスメを知りたい
なるほど。反対の意味の言葉を使うことで、どのように印象を測るのですか?

コスメ研究家
それぞれの言葉の間には段階があって、例えば『とてもさっぱりしている』『ややさっぱりしている』『どちらでもない』『ややしっとりしている』『とてもしっとりしている』のように、自分の感じ方に合ったものを選ぶんだ。そして、その結果を数値化して、グラフなどで見やすくするんだよ。
言葉で表す使い心地

毎日使うものだからこそ、気持ちよく使える化粧品を選びたいですよね。化粧品の良し悪しを決める要素は、成分や効果だけではありません。「さっぱりとした使い心地」や「しっとりとした質感」といった、実際に肌で感じたときの心地よさも大切なポイントです。
しかし、このような感覚的な印象を言葉で伝えるのはなかなか難しいものです。「さっぱり」と感じる度合いは人それぞれですし、「しっとり」と「ねっとり」の違いを明確に説明するのも容易ではありません。
そこで役に立つのが、SD法と呼ばれる手法です。SD法は、人の感覚を数値化し、グラフや図を用いて視覚的にわかりやすく表現する方法です。例えば、「さっぱり感」を数値で表すことで、複数の化粧品を比較検討することが容易になります。また、「しっとり感」と「べたつき感」の関係性をグラフで可視化することで、それぞれの化粧品の特徴をより深く理解することができます。
このように、SD法を用いることで、これまで曖昧であった感覚的な印象を客観的に捉え、自分にぴったりの使い心地の化粧品を見つけることができるようになります。
| 化粧品選びのポイント | 課題 | SD法による解決策 | メリット |
|---|---|---|---|
| 使用感(例:さっぱり感、しっとり感) | 感覚的な表現は個人差があり、伝わりにくい。 | 人の感覚を数値化し、グラフや図で視覚的に表現する。 | * 複数の化粧品を比較検討しやすい。 * 化粧品の特徴を客観的に理解できる。 * 自分にとって最適な化粧品を見つけやすい。 |
反対の意味を持つ言葉で評価

化粧品の使用感を評価する際に、言葉で表現することの難しさを感じたことはありませんか?感覚的なものを伝えるには、具体的な数値や指標だけでは不十分な場合があります。そこで役立つのが、「SD法」と呼ばれる評価手法です。
SD法では、「さっぱり」と「しっとり」のように、反対の意味を持つ言葉を両端に配置した尺度を用います。例えば、ある化粧水を使った後に感じる肌の感触を評価したいとします。評価者は、「さっぱり」と「しっとり」の両端を見ながら、自分の感覚に近い位置に印を付けます。
「とてもさっぱり」だと感じれば左端に印を付け、「とてもしっとり」だと感じれば右端に印を付けます。そして、「どちらかといえばさっぱり」や「ややしっとり」のように、中間の度合いによって、間の段階を選びます。
この方法の利点は、言葉の持つイメージを借りることで、感覚的な状態を分かりやすく表現できる点にあります。数値化しにくい「使用感」を評価する際に、有効な手段と言えるでしょう。
| 評価項目 | 尺度 |
|---|---|
| 肌の感触 | さっぱり | | | | | しっとり |
数値化で比較しやすく

化粧品の使用感を伝える言葉は、人によって捉え方が違うことがあります。「さっぱり」と感じる度合いも人それぞれですし、「しっとり」の感じ方も異なるでしょう。このような、言葉で表現された評価の曖昧さを取り除き、より客観的なデータとして扱えるようにするのがSD法です。SD法では、言葉による評価を数値に変換することで、個人差によるばらつきを減らし、評価の客観性を高めます。
例えば、「さっぱり感」を評価する場合、完全に「さっぱり」を1点、「ややさっぱり」を2点、「どちらでもない」を3点、「ややしっとり」を4点、完全に「しっとり」を5点といったように、段階ごとに点数を割り当てます。そして、複数の被験者に製品を試してもらい、それぞれの項目に対する評価を数値で答えてもらいます。こうして集めたデータを統計処理し、平均値を計算することで、「この製品は平均3.8点で、どちらかというと『しっとり』よりの使い心地である」というように、製品全体の印象を数値で表すことができるようになります。 このように、SD法を用いることで、言葉では曖昧になりがちな感覚的な評価を、数値化して客観的に比較分析することが可能になります。
| 評価 | 点数 |
|---|---|
| 完全に「さっぱり」 | 1点 |
| ややさっぱり | 2点 |
| どちらでもない | 3点 |
| ややしっとり | 4点 |
| 完全に「しっとり」 | 5点 |
グラフで見てわかる結果
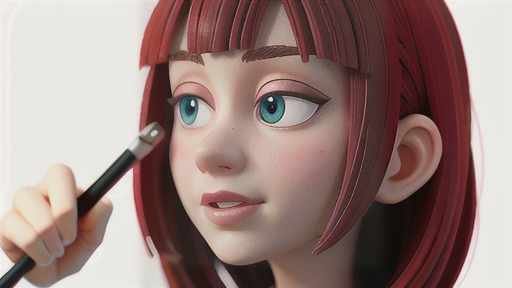
– グラフで見てわかる結果化粧品の研究開発において、消費者の感覚的な評価を数値化することは非常に重要です。例えば、新しい化粧水を開発する際に、「みずみずしい」「しっとりする」「べたつかない」といった使用感を数値で表すことができれば、客観的なデータに基づいた製品開発が可能になります。このような数値化を実現する手法として、SD法(Semantic Differential Method 意味差判別法)が広く用いられています。SD法では、評価対象となる製品に対して、相反する二つの形容詞(例みずみずしい⇔しっとりする)を設定し、その間に複数の段階を設けて、消費者にどちらの形容詞に近いかを選択してもらいます。そして、得られた回答を集計し、平均値を算出することで、製品の使用感を数値化します。SD法で得られた数値データは、そのままでは解釈が難しい場合もあるため、レーダーチャートや折れ線グラフなどを用いて視覚化することが一般的です。これらのグラフを用いることで、複数の製品の特性を比較したり、開発中の製品が目標とするイメージにどれだけ近づいているかを客観的に判断したりすることが可能になります。例えば、新しい化粧水の「みずみずしさ」を評価する場合、従来品と比較して、どの程度「みずみずしい」と評価されているかをグラフで確認することができます。また、開発中の化粧水が「みずみずしい」というだけでなく、「べたつかない」という点も両立できているかを、複数の項目を同時に表示できるレーダーチャートで確認することもできます。このように、グラフを用いることで、数値データだけでは見えてこない製品の特徴や開発の課題を明確化することができ、より効果的な製品開発につなげることが可能になります。
| 手法 | 説明 | メリット | グラフ化 |
|---|---|---|---|
| SD法 (意味差判別法) |
相反する形容詞の間に段階を設け、消費者に近いものを選択させることで、感覚を数値化する。 | 客観的なデータに基づいた製品開発が可能になる。 | レーダーチャートや折れ線グラフで視覚化することで、製品の特性や開発課題を明確化できる。 |
製品開発に役立つSD法

– 製品開発に役立つSD法
化粧品は、ただ効果があるだけでなく、使う人が心地よさや楽しさを感じられることも大切です。しかし、人の感覚は言葉で伝えるのが難しく、開発者の思いと消費者の感じ方の間には、どうしてもずれが生じてしまいます。
そこで役に立つのがSD法です。SD法とは、人の感覚を言葉ではなく、図形やグラフなどを用いて視覚的に表す手法です。例えば、「この化粧水はさっぱりしている」という感覚を、図の上で「さっぱり」と「しっとり」の間に点を打つことで表現します。
化粧品メーカーでは、新製品や改良品の開発段階で、このSD法を用いるケースが増えています。多くの消費者の意見をSD法で収集し、分析することで、「消費者がどのような使い心地を求めているのか」を、感覚的に捉えることができるからです。
開発者は、得られたデータを元に、配合成分やテクスチャーなどを調整し、消費者の感覚に寄り添った製品作りを進めます。このように、SD法は、開発者の想いと消費者の感覚を繋ぐ架け橋となり、より満足度の高い化粧品を生み出すために役立っているのです。
| 手法 | 目的 | 方法 | メリット |
|---|---|---|---|
| SD法 | 化粧品開発において、開発者の想いと消費者の感覚のずれをなくす | 人の感覚を言葉ではなく、図形やグラフなどを用いて視覚的に表す。 例:
|
|










